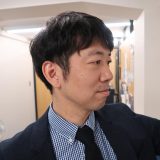※この記事は、地域づくり情報誌『かがり火』175号(2018年6月25日発行)に掲載されたものを、WEB用に若干修正したものです。
誰もが唯一、固有な物語を持っている
私たちが日ごろ目にする本や雑誌には、珍しい体験をした方の話や、特別な体験をした方の話がたくさん紹介されています。15年前、私はライターとして、多くの方の共感を呼ぶような記事、多くの人を感動させるような本を作るために取材をし、文章を書いていました。
そうやって本や雑誌には、作り手が「特別」であると認めた活動や人生が紹介され、読む人にヒントやアドバイス、共感や感動を与えていきます。そういうものなのだと漠然と思ってはいましたが、一方で、何か大きなものが抜け落ちた世界をつくっているような気持ちも持っていました。
本来、人の人生には特別も平凡もありません。どの方の人生も固有で唯一のもの、特別なものです。なのに、記事や本になって誰もが読めるものになり、後の世代まで残るのは、一部の人たちが選んだ話だけです。
ほとんどの方の人生や出来事は、残された人のそれぞれの想い出の中で、切れ切れのかけらだけを残して、やがて消えてしまいます。そういうものなのかなと、もったいなさ、寂しさを感じていたのです。
考えてみれば、私たちは、親や、その世代の人たちの暮らしや人生を本当に驚くほど知りません。さまざまな想い出は、写真やフェイスブックの投稿に残っていたとしても、その時にどう感じていたのか、心に残っているのはどんなことなのかは、誰にも伝わることなく消えていく。それでいいのだろうか、と。
誰の人生も、起こった出来事も、やがては消えていく、それだからこその美しさもあるとは思いながらも、残したいと思う気持ちを強く持つようになっていました。
つらさも哀しみも、思い出話として語られる時には美しい物語になっているのに。
例えば、特別な体験や、とっておきの話、会社をつくった時のこと、家を建てた時のこと、親のこと、子どものことを、話して残しておく。それはやがて誰かの役に立つかもしれません。
「あなたのお話を聞いて文章にするお手伝いをします」、そんな見出しを付けたチラシを作ったのは、今から15年前のことです。
有名な人や特別なことをした人ではなく、「普通」と思われている方、自分のことを普通だと思っている方の話を聞いて残すお手伝いをしたい。できれば、読めるものにして、5冊、10冊、あるいは1冊だけの冊子にしたい。それが「私的小冊子─プライベートリーフレット」作りを始めることになった発端です。
ただ、それを形にして具体的に進めていく力が、そのころの私にはありませんでした。フリーライターとしての収入が不安定で、新しいプロジェクトを立ち上げる余裕もなく、生活のための副業として飛び込んだ介護の仕事が、徐々に本業となっていったからです。
介護の仕事を通して
たまたま機会を得て訪問介護員の資格を取得していたことで、副業として選んだのは、認知症の方の生活を支える仕事でした。何もかもが初めてで、戸惑うこともありましたが、仲間に恵まれたこともあり、それまでとはまったく異なる、やりがいや喜びを感じるものでした。
介護の仕事を3年間すると、国家資格である介護福祉士の受験資格が得られます。私は認知症や障害者の方をケアする資格などを立て続けに取得しました。
介護の世界でさまざまな現場を経験しながら、十数年たったころにはケアマネージャーの資格も取り、大阪市西成区にある事業所でケアマネージャーとしての仕事に就きました。
介護の仕事というと、食事や入浴、排せつのお世話をすることだろうと思われるかもしれませんが、現在の介護職は、報告や記録、プラン作成、研修など、デスクに向かってする仕事も相当量しなければなりません。
介護を受けるご本人やご家族と過ごし、お話をすることも大事な仕事でした。特に介護サービスの利用を始められる前には、介護計画を立てる際の参考とするために、それまでの生活や家族構成、職業歴、病歴などの話を伺うことが不可欠です。
介護の職場で責任者として、私は再び、さまざまな方のお話を伺う機会をたくさん持つことになりました。
高齢の方は、言うまでもなく長い歴史を経て現在に立っておられます。出生の話から始まり、子どものころの話、仕事の話、結婚などに加えて戦争や大きな災害など特別な体験談もあって、語られるお話は大抵、壮大なものとなりました。
もちろん、どの方も、聞けばどんどん話してくださるかというと決してそんなことはありません。むしろ、いきなり切り込んでいき、拒絶させることも少なくありませんでした。ライターの経験があり、人の話を聞くことに慣れているはずの私でしたが、大阪市西成区で働き始めた時には特に苦労をしました。
西成区には、釜ヶ崎、あいりん地区と呼ばれる地域があり、それまで私が出会ってきた人たちがしたことのない経験をしてきた方や、独自の人生観を持っている方が多くおられました。
「ご家族はおられますか」「どんなお仕事をされてきましたか」と伺っても、なかなかすぐには答えていただけません。笑顔で迎えてくださっていたのに質問を始めたとたんに硬い表情になる方、「言いたくない」とはっきり拒絶される方、「関係ないやろ!」と怒鳴る方もいました。
「それぞれ、いろんな事情があってこの町にきた人ばっかりや」。そんな言葉を聞き、無理やり聞き出すことで関係が悪くなるよりはと、書類には「過去については話すのを拒まれる」などと記していました。
しかし、ことあるごとに訪問し、通院や入院時の面会などで一緒に過ごす時間が長くなってくると、話すともなく語られる想い出話を聞くことが、思いがけず増えていきました。
語られる内容は、わけあって離散した家族の話、過去に犯した罪のこと、償った日々のこと、また高度成長期のとんでもなく景気のいい話など、正直、驚かされる内容の話が少なからずありました。
長く話した後、「しょうもない話、聞かせて悪かったな」「こんなに話したのは何年ぶりやろ」「話してたら、いろいろ思い出してきたわ」そんなことを言われ、胸が熱くなるようなこともありました。
介護の仕事を通して出会った方々のお話を聞いてきた経験を通じて、15年前に抱いた私的小冊子を作りたいという思いは、より強くなったように感じています。
ライターとしてではなく、介護職として出会った特別ではない人たち、専業主婦だった人、サラリーマンで定年を迎えた人、小さなお店を守ってきた方々の、活字にはなってこなかったようなお話の中にこそ、文章にして残したいと思う物語がたくさんあったからです。

落ちこぼれだった私の話も少し
人の話を聞いて文章にしておきたいという気持ちは、私自身のそれまでを思い返し、そう言えばいろいろあったなと懐かしむ気持ちも呼び起こしました。
今でこそ、多くの資格を持ち、リーダーとして仕事をしたり、教える側に立ったりしているので、私のことをエリートだと勘違いする人もいるのですが、小学校、中学校と、私は勉強にも、学校のシステムにもまったくついていけない完全な落ちこぼれだったのです。
今なら発達障害だと診断され、適切な対応がされたのかもしれませんが、私の時代には、ただ知能が低く、理解力も落ち着きもなく、努力ができない子どもだと思われていただけでした。
親からも先生からも、怒られたり、首をかしげられたりするばかりで、そのころのことを思い出そうとしても、私には、まるで霧の中に一人でいるようだった記憶しかありません。
走ったり飛んだりでは、周りを驚かせるほどの記録を出し、習っていたバレエやオルガンではそこそこの力を発揮していたこと、本を読むことが好きだったことが救いにはなっていましたが、楽しさやうれしさを感じることは少なかった子ども時代でした。
不思議なことに、その後、社会に出てからは、そのようなことがなくなり、職場では何でもスムーズにこなせたので、日々が楽しくなりました。
何よりも、ばかにされることがなくなり、私自身も自分がばかではなかったのだなと思うことができたことが不思議かつうれしく、さまざまなことに積極的に関わるようにもなりました。
学ぶ楽しみを初めて知ったような日々の中で、縁ある方々からさまざまなことを教えてもらったり、学ぶ機会を与えてもらったことも幸運だったと思います。
また、自分で目標や方向を決めたわけでもないのに、たまたま職場の業態変更に応じて、塾講師の仕事や、プログラミング、文章作成などを断らずに引き受けたことがムダにならず、新しい仕事へ、次の段階へとつながっていったということもありがたいことでした。
現在は、介護職員になる人のための研修の場で講師として勤めています。その傍らで、あらためて本当にやりたかったことを本業として残りの人生を生きたいと思った時、15年前に思い立ったことが実現できる状況になっていることに、いちばん驚いているのは私自身だと思います。
救いようのない落ちこぼれが、何とか社会で活躍できるようになった体験も、きちんと残しておけば、どこかで誰かの役に立つかもしれませんね。

母の話でさえ知らないことばかり
15年前、インタビューして聞かせてもらった話を、わずかな部数の冊子にして届ける仕事をしたいと思った時、手始めにと、母にインタビューを試みたことがあります。母が70歳、私が43歳の時のことです。
数時間をかけて、生まれた時のことから話を聞いていきました。聞きながらまず感じたことは、それまで母の話を真剣に耳を傾けて聞いたことなどまったくなかったということでした。
何度となく聞いてきたエピソードがあるにはありましたが、幼かったころに見た風景、戦争をめぐる話、恋愛の話、これまで人に話したことがなかったという苦労話などが、しっかりと聞くことで初めてつながり、初めて母の歴史を知り、人生観の根底にあるものが浮かび上がってきました。
それによって、母と娘として、どこか近づけないまま、あるいは納得できないままだったことを理解できたことは、私にとってこの上なくうれしいことでした。
一方の母は、話をしたことは楽しんでくれたようでしたが、出来上がった文章にはそれほど興味を示すことがありませんでした。自分のことを自分で話しただけのことと思えば、無理のないことだったかもしれません。自分の話は自分では価値があると思えない、そういう特徴があるようです。
その時のインタビューテープが今、手元にあります。昨年、突然亡くなってしまった後にインタビューのことを思い出し、探したものです。まだ聞く機会は持てていませんが、あの時きちんと話を聞いておいて本当によかったと思っています。聞いた話とテープは大切な宝物です。
残さなければ消えてしまう
老親の話を、あらためてじっくりと聞いたことで、プライベートな話や、当たり前の出来事の話ほど、残しておかなければ消えてしまうのだということにも気が付きました。
親の話は子どもにとっては特別ですが、世間に広く価値を持つものではないので、大切に取っておこうと思われることはありません。しかし、残された写真が子どもの支えになるように、残された言葉や文章があれば、時を超えて教えられたり、勇気づけられたりすることがきっとあるはずです。
「普通」のものや当たり前のことは、ことさら大事に取っておこうとされない、そのことで私たちはたくさんの大事なものを失ってきたのではないでしょうか。今だからこそ、消えつつあるものに目を向け、残していくことの大切さを考えたいのです。
最近になって、出会う方にそのような思いを伝えると、それならばと、ご自身やご両親の話をとおっしゃることがよくあります。それらを一つずつ、形にして残すお手伝いをしていく、それが今の私に与えられた大切な仕事だと思っています。
(おわり)
『かがり火』定期購読のお申し込み
まちやむらを元気にするノウハウ満載の『かがり火』が自宅に届く!「定期購読」をぜひご利用ください。『かがり火』は隔月刊の地域づくり情報誌です(書店では販売しておりません)。みなさまのご講読をお待ちしております。
年間予約購読料(年6回配本+支局長名鑑) 9,000円(送料、消費税込み)