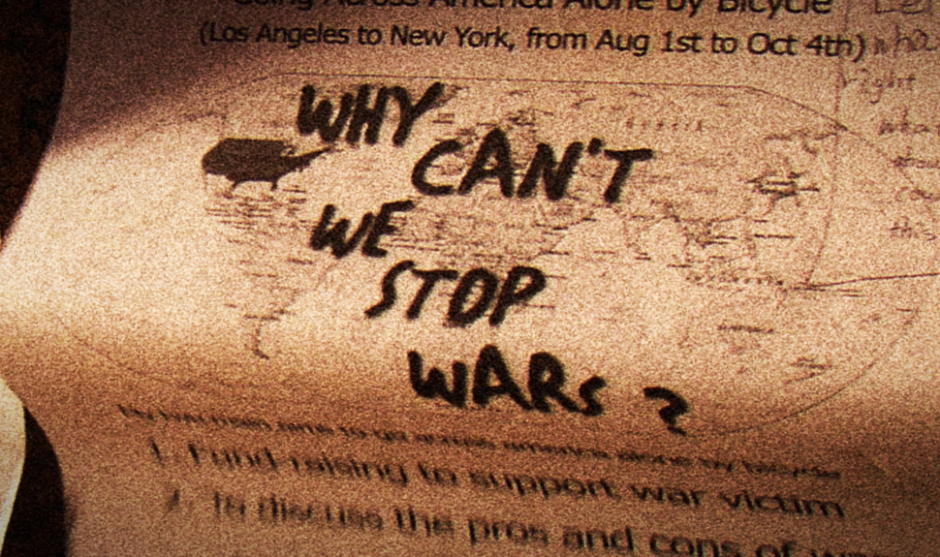ユダヤの眼差し
「どこから来たんだ?」
「大学では何の勉強をしているんだ?」
最初はあたり障りのない会話だった。その老人がぼくに話しかけてきたのはスーパーマーケットの駐車場でだった。小さなトラックから顔をのぞかせ、自転車を止めていたぼくに声をかけてきたのだ。
手や顔には深いしわが刻まれている。七十歳を優に超えているだろう。話し方は穏やかで、その眼差しに何かしら聡明さのようなものを感じた。
モーテルで自転車を盗まれてから数日が経っていた。あの朝、ぼくは数時間かけてなんとか現実を受け入れ、警察に届けを出し、保険会社に連絡をした。そして盗まれた自転車への未練を捨て、次の日に盗難保険で新しい自転車を買った。これで大丈夫なのか、という不安は全く拭えなかったが、旅の準備だけはしていった。そして、いくつかの備品を揃えるために、海沿いのスーパーマーケットに来ていた。老人と出会ったのは、その駐車場でだった。
“WHY CAN’T WE STOP WARS?”
ぼくが渡したフライヤーの大きな文字を老人は眺めている。
それは日本で準備を手伝ってくれた友人が考えだしたフレーズだった。アメリカに行って、初対面の人との対話のきっかけを彼は一緒に考えてくれていた。
「日本から自転車を積んで飛行機でやってきたのか?」
つい昨日、アメリカに着いたばかりだとぼくは話した。
「君はたった一人でこの反戦運動をやろうとしているのか?」
日本に何人かの仲間がいるが、反戦運動というより、人々の意見を聞いて考えるきっかけにしたいのだと話した。考えるきっかけにしたい。煮え切らない表現だが、それが当時ぼくが思っていたことだった。
「そうか」と、ため息混じりに鋭い視線を浴びせてくる。彼は明らかに何かに苛立っているようだったが、ぼくにしてみればアメリカに来てほとんど始めてまともに会話をする人間だった。もう少し話を聞いてみたかった。
「いったい何日かけて横断するんだい?」
「二ヶ月くらいの予定です」
老人は左右に首を振りながら、チッチッチッと小さく舌打ちする。
「自転車でこの国を横断しても、真ん中には何もありはしない。この国は東海岸と西海岸に人口が密集しているんだ」
少し不愉快になってくる。ぼくは彼のそぶりから、これからの会話がどんなものになるのかわかるような気がしていた。アメリカにやってくる前、日本でもあら探しをしては難癖をつけるような人がいたのを思い出したのだ。
出発前、旅の準備をしていたときのことだった。大学のひとつ下の後輩がぼくのところにやってきて言った。
「先輩は戦争の被害者をサポートしようなんて考えているみたいですけど、それはどちらかというと偽善か売名行為に近いですよね」
あざ笑うような挑戦的な口調でひとこと、吐き捨てるようだった。彼はふだん仲の良い後輩だっただけに、きついことを言われ、ショックだった。なんと答えればいいのかわからなくなって、呆然となって逃げるようにその場をあとにした。
仲間と何ヶ月もかけて準備を進めてきたプロジェクトは、偽善でしかないのか。もうこんなのはやらなくていいんだ。そう思って準備中だった旅をすべて投げ出してしまおうかとも考えた。
それ以降、同じような事を言われる度に、自分を納得させるための言葉を探し始めた。
自分は別に善人に近づこうとしているわけじゃない。だからたとえ偽善でもやめる理由にはならないのだと強がってみたり、サポートを必要としている人は、それが善意によるものかどうか吟味する余裕さえないはずだと考え直してみたり。
あるいは「誰かを救うことのできる偽善と、何もしない善意、どちらが本当の偽善なのか考えてみるべきだ」と、次に言われたらそんな風に返してやろうと息巻いていたりもした。
言葉という鎧で身をかためれば、少なくとも自分を守ることができる。出発前、そうしなければ前に進む事ができなかった。誰かに間違っていると言われてそれ以上何も言えなければ、自分自身を納得させることさえできず、そこで終わってしまうのだ。あとから考えてみれば出発前のぼくはそんなふうに色々なことに怯えていた。そして怯えながらもなんとか出発できたのは、自分の中に善とか偽善とかとは全く別の理由がある気がしていたからだ。だがその「別の何か」が自分の中できちんと言葉になるのはもっと後のことだった。
「戦争はなぜなくならないのか?いい質問だ、若者よ」
やがて老人は車の窓枠に肘をかけ、身を乗り出すようにしてゆっくりと話し始めた。
「残念ながら戦争はなくならない。戦争を憎む君の気持ちはわかるよ。しかし、争いというのはある意味で人間の内側に宿る本質だ。私は君の何倍もの長い時間をかけていろんな人間を見てきた。色々な国の歴史も民族も文化も宗教も学んだ。若い頃には兵隊として戦争にも行ったよ。そうして長いことかけてわかったことがある。人間は一方で愛や平和を唱えておきながら、同時に自分を正当化するために矛盾を犯すものだということだ。人間というのはどうしようもなく腹が減れば人からものを奪ってでも生きようとするし、そのために人を殺す場合だってある。それが良いとか悪いとかではなくて、人というのは状況によってそうした行動をとってしまうものなんだ」
人間の本質をつくよどみない言葉。ただ黙って聞いていた。老人はシニカルに構えている。ぼくは何となく反抗精神のようなものをぶつけてみたくなった。ただ、それが喉元まで出かかっていたのだが、なぜか口をつぐんでしまった。老人はさらにたたみかける。
「戦争だって同じだよ。人種に優劣をつけたり金や資源を手に入れるために武力を使うんだ。歴史上の多くの戦争も背後にはそうした人間の性質が必ず見え隠れしている。私はユダヤ人で君は日本人だが、それはたいした違いではない。みんな同じだよ。何千年も昔から人間にはそうした遺伝の記憶が受け継がれている。血とでもいうのかな。もちろん君にもだ」最後の一言が挑戦的に響いた。
そばの駐車場では女の子がアイスクリームをなめながら母親と車に乗ろうとしていた。そして何かの加減で、アイスクリームがコーンからずるりと滑って地面に落ちてしまった。女の子が急に泣き出し、母親があわてて慰める。そんな安穏を尻目に我々の会話は続いた。ぼくは少しエキサイトしつつも、彼とのあいだに感じる深い溝のようなものが一体何なのかと想いをめぐらせていた。
「今のアメリカを見てごらん。ブッシュは中東のイラクに自由を与えるとか、大量破壊兵器の撲滅だとかいろんな理由をくっつけて戦争を始めているけど、あれは建前に過ぎない。裏では石油や金が権力とともに蠢いているんだよ。敢えてそれを深く追求しようとする人間も少ないのだけれどね」
老人の口からたんたんと語られる言葉はどれほど正確にこの国を描写しているのだろう。けれどもそれがこの国の市民の目を通して語られるアメリカの一部であることに変わりはない。そして、ぼくは後に彼と似たような意見を口にする人々に少なからず出会うことになる。
言いたいことを言い終えたのか、老人は諭すような眼でぼくを見ていた。そして間があいたのをきっかけに、ぼくも自分の考えを少しずつ話し始めた。人間は非暴力運動や核廃絶、銃規制といったかたちで、常にそういった暴力を自制する努力も続けてきたし、矛盾や欲望や暴力的な側面があったとしても、それを戦争という手段に転化しないための努力はしてきたのではないか、と。
「しかし、歴史を見てもわかるようにそれらの運動は常にうまくいかなかったんだ」
うまくいかなかったというのは、それらの運動は無意味だったということなのだろうか。少なくともそれらの運動で助かった無数の命も歴史上に存在したのではないのだろうか。ぼくはそのときインタビューという一定の距離感を越えて、なぜか自分自身がぶつかっていくような気持ちになっていた。
「その通りだ。君に反対しているわけじゃない。戦争に疑問を持ったり、募金を集めたりするのは正しい。しかし、それは絶望的な道でもあるんだ」
絶望的。彼の苛立ちの奥に潜むものが何なのか、わかりかけてきた気がした。戦争はないにこしたことはないが、「戦争反対」と叫んでみることの無意味さをきっと彼は嘆いているのだ。彼はぼくに対して苛立っているのではなく、その絶望に苛立っているのだ。
ユダヤ人である彼は、第二次大戦ではアメリカ兵として闘っただけでなく、ナチスに大量に仲間を殺されもした。戦後アメリカが朝鮮、ベトナム、湾岸といろいろな戦争をやり、故郷であるはずのイスラエルも何度となく戦火にまみれた。それを考えれば、彼らほど戦争に絶望している人々もいないのだろう。
半世紀以上にわたって人類の愚行を眺めてきた彼にとって、たしか戦争に疑問を持ってみたところで虚しいだけのことかも知れない。
きっとユダヤ系アメリカ人である彼は世界で最も戦争に絶望している一人であり、日本の若者であるぼくは世界で最も平和を楽観視している一人なのかもしれない。ぼくは彼との間に横たわっている溝の深さが何であるのか、少しわかりかけた気がした。
ふと彼がアラブの人々やイスラム教徒のことをどう思っているのか気になった。アメリカに六百万人いると言われるユダヤ人の数は本国イスラエルよりも多いという。
「ユダヤもアラブもない。問題は人間のさがにある。彼らはそれを人種の問題にすり替えているだけだ」
なるほど。しかし肝心のさがとは一体なんなのだろう。
「相手よりも自分が優位に立とうとする性質だ。それは人間の内に潜む不安と関係がある。君の中にもそれはあるはずだ。そうだろう?」
老人の射抜くような眼差し。思わず頷いていた。老人はもう一度、つぶやいた。
「絶望的なんだ」
ぼくは改めて聞いたその言葉がやはり腑に落ちないようで、言ってみた。
「わかっています。でも何もやらないより少しでも何か考えたり行動した方が、小さな一歩になると思ったんです」と。
しかし言ってみたものの、その言葉は老人の前で虚しく響いた気がした。老人の年月を重ねたうえでの厳しい現実認識のことを、本当にわかっているだろうか。ぼくはそのことに自信がなかった。
「その通りだ。確かに君にとっての第一歩だ。だから君は今よりももっともっと力をつけなければならないね。今よりもたくさんの仲間を集め、表現力を高め、多くの人に君の考えを伝えられるようにならなければいけない。ドキュメンタリーのフィルムを作ったり、本を書いたり、アートでもいい。その方法はいくらでもあるし、若い君にはそれを探す時間もたくさんある。ただ、今よりも力強くならなければならないよ。例えばマイケル・ムーアがやってみせたようにね。ほら、今ちょうどシアターで『華氏911』をやっているだろう。君も見てみるといい」
『華氏911』は『ボウリング・フォー・コロンバイン』でアメリカの銃社会に疑問を投げかけたマイケル・ムーア監督が9・11以降のブッシュ政権の政策や戦争を批判したドキュメンタリー映画だ。アメリカはおろか、世界中が注目するこの映画監督は十月に行われる大統領選挙でのブッシュ大統領の再選を食い止めるために全力を尽くす、と豪語していた。
「君はまだ大学生だ。とても若いし行動力もある。それは大きな可能性に満ちているということだ。何年もかけて自分のやり方をじっくりと探すんだ。長い道のりだけれどね」
老人の話し方は、最後に少しだけ優しくなった。そしてその分、重く響いた。たった六十日のアメリカ横断に不安を覚えている自分にとって、大学を卒業したあとの仕事さえ決まっていない自分にとって、彼の言う「可能性」は、とても不確かなものに思えた。
いったいぼくはこれから戦争についてどれほど粘り強く関与してゆけるのだろう。そう考えるとき、ある女性の言葉が頭をよぎった。出発前、「セーブ・ザ・チルドレン」というNPOを訪問したときに、担当のワタナベさんという女性が言っていた。
「私は土曜の夜になるとたまにお酒を飲んだりする。そのお金で誰かを助けたりできるかもしれないって思いながらね」
何気ない雑談の中のひと言だったが、後々まで印象に残っていた。彼女の中に決して均衡点を見出せない両極がシーソーのように揺れ続けており、そのシーソーはある種の重苦しさを放ちながら自分の中にもあるのだと思えたからだ。戦争について考え続けることは、その問いの重さに耐えていくことと共にあるのかもしれない。ぼくにはそれができるだろうか。
そんなことを考えるうちに、何か自分の小ささのようなものを感じ、言いようのない所在なさがこみ上げてきた。もしかすると自分はこんなプロジェクトをやって、本当にただいきがっているだけなのかも知れない。
ぼくは最後に一冊のノートを取り出して、老人に何かメッセージを残して欲しいと頼んだ。彼は快く引き受けてくれ、ノートを渡すと迷うことなくペンを走らせた。書き綴りながらそれらをひとつひとつ穏やかに読みあげていた。つぶやくような言葉は、ぼくにというよりは自分に言い聞かせているようでもあった。
書き終わると、「気をつけてな」と言って老人はスーパーの駐車場を離れた。老人のトラックが見えなくなるとぼくは受け取ったノートに目をやり、今しがた彼が残していったメッセージを読んでみた。
君の前に立ちはだかる大きな壁が見える
君は平和を愛するという様々な人種や宗教の人々に出会うだろう
しかし本当のところ彼らは己の立場を正当化しているに過ぎないのだ
流れるような筆記体で書かれたその文字は、すぐれた書家の作品のような優美さをたたえながら、人間の内に潜む暗い性を鋭く照らしているようだった。
様々な気持ちが駆け巡っていった。戻ることのできない場所に足を踏み入れたような重苦しい感覚。ものごとの深みを自分だけが垣間みたような満足感。駐車場を離れるころ、ぼくはこの国と人間のことをもっと知りたいと思うようになっていた。
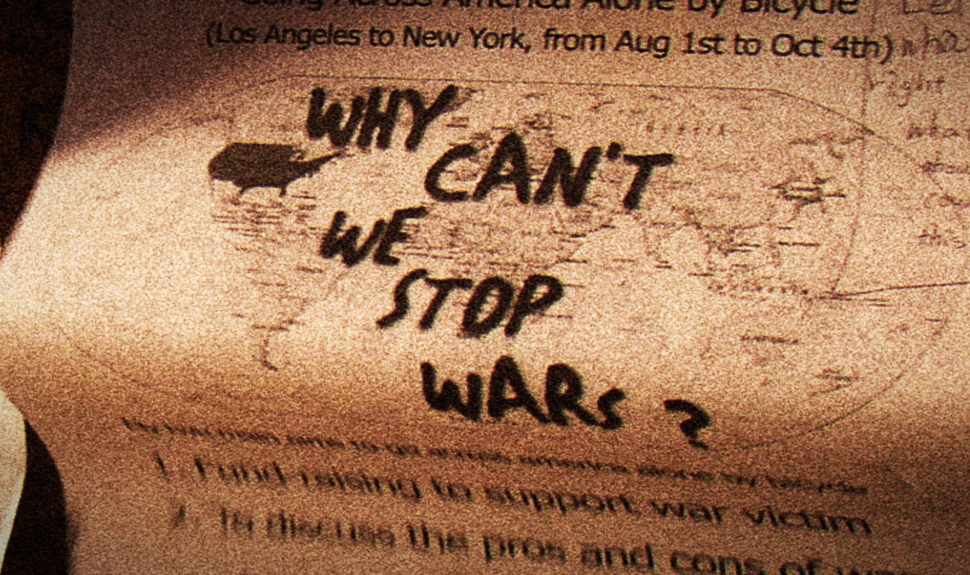
(つづく)
<目次>
【プロローグ】―なぜ戦争はなくならないのか―
【第一章・洗礼】―翌朝目が覚めると、さらに厳しい現実があった―
【第二章・ユダヤの眼差し】―「ユダヤもアラブもない。問題は人間のさがにある」―
【第三章・海辺の墓標】―怒りを訴えたいのか、悲しみを訴えたいのか―
【第四章・救命者の矛盾】―「自由を守るという物語に流されていったのよ」―
【第五章・渇きの果てに】―それらはあたかも暗い宇宙につつましく瞬く生命の輝きのようでさえあった―
【第六章・荒野の漂流者】―「日本でまた会おう」彼の言葉だけが耳の奥でリフレインしていた―
【第七章・逆境の中の生命線】―「闘いは嫌いだ。でも彼らをリスペクトしている」矛盾しているとぼくは思った―
【第八章・自由とは何か】―「自由万歳」を置き換えてみるとわりとよくわかる―
【第九章・オクラホマの風の中で】―彼女はこの場所でぼくと同じ歳で亡くなった―
【第十章・地図の上の1セントコイン】―それは戦争の是非を問うことと同じくらい大切なことに思えた―
【第十一章・ある記憶との闘い】―私は弱さを持った人間を探していた。どこかに自分と同じような人を探していたのよ―
【第十二章・シェルター】―ぼくは「彼ら」から逃げない人間になりたい―
【第十三章・マイノリティの居場所】―“There is no way to Peace,Peace is the way.A.J.Muste”―
【第十四章(最終章)・無限のざわめきの中へ】―その豊かさは残された救いのようでさえあった―
【著者プロフィール】
矢田 海里(やだ かいり) ライター・フォトグラファー。1980年、千葉県生まれ。慶応義塾大学総合政策学部卒。在学中、イラク戦争下のアメリカ合衆国を自転車横断しながら戦争の是非を問うプロジェクト“Across-America”を行い、この体験を文章にまとめたアクロス・アメリカを執筆。フィリピンのマニラのストリートに潜入し、子どもたちや娼婦たちの暮らしを見つめ、ルポルタージュを執筆中。東日本大震災発災直後に現地入り、ボランティアの傍ら現地の声を拾い始める。以降現地に居を構えながら取材を続ける。放送批評雑誌『GALAC』に「東北再生と放送メディア」を連載。冒険家やアスリートを紹介するサイト「ド級!」でエクストリーマーの一人に選ばれる。「不確かさと晴れやかさのあいだ」をテーマに人間の内面を描き続けている。
『かがり火』定期購読のお申し込み
まちやむらを元気にするノウハウ満載の『かがり火』が自宅に届く!「定期購読」をぜひご利用ください。『かがり火』は隔月刊の地域づくり情報誌です(書店では販売しておりません)。みなさまのご講読をお待ちしております。
年間予約購読料(年6回配本+支局長名鑑) 9,000円(送料、消費税込み)