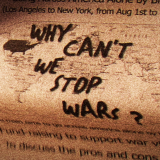海辺の墓標
ユダヤの老人と別れて数十分、印象的な言葉がまだ脳裏にリフレインしていた。興奮が冷める前に、次の誰かと話したいと思っていた。ユダヤの老人のように話しかけてくれればよいが、次はこちらからアプローチしなければいけない。けれどもぼくはそのきっかけを掴めないでいた。
というのも、右も左もわからないアメリカの街では、すべてが新鮮である反面、どこにいても場違いな感じがしたからだ。そして何よりも、何気ない人々の暮らしの中に入っていって、突然戦争の話を聞かせてほしいと切り出すのはとても勇気のいることに思えた。
フライヤーを渡し、興味を持ってくれた人にインタビューを試みる。そんな行為が不自然でないような、活気のある場所を探していた。
ロスの街を走り回り、やがて有名なサンタモニカのピアのそばまでやってきた。午後のビーチが観光客や散歩を楽しむ人々でごった返している。ここならどうだろうか。
自転車を降りてビーチから海へ突き出た大きな桟橋の方へ歩いていった。桟橋の上には土産物屋や小さなローラーコースターやメリーゴーランドがあって、ちょっとした遊園地のようになっていた。そばで水着の子供たちが走り回っている。
賑わう人々と自分の持っているフライヤーを交互に眺めた。華やかな笑顔と「なぜ戦争はなくならないのか」というロゴ。コントラストというよりは、やはり違和感に近い。
土産物屋の入り口でヒッピーのような長いひげの男が、シャボン玉を吹いている。その周りをはしゃぎ回る子供たち。シャボン玉が風に乗ってぼくの目の前で割れた。
ぼくは戸惑い、こんな場所でいきなりビラなど渡したら空気を読めてないだろうと思いながら、ピアのあたりをうろうろと歩き回っていた。
しかし桟橋のたもとまで戻ってくると、来た時は気づかなかったものが目に入った。ビーチの一角に無数の白い小さな十字架が立てられているのだ。潮風に乗って鎮魂歌のような音楽も聞こえ、星条旗がたなびいているのも見えた。周囲にはちょっとした人垣もできている。
直感的に、何か自分の活動と近いものを感じた。砂浜の一角が放つ磁場のようなものに吸い寄せられるように近づくと、それはどうやら戦没者の十字架らしかった。何の戦没者なのか、詳しいことはわからなかったが、ここならフライヤーを配っても違和感はないと思えた。一人ではできないのかと情けなくもあったが、とにかく持っていた数十枚のフライヤーを手に、人垣の中に立った。果たして人々はどういう反応を示すのだろう。ぼくはおそるおそる最初の一枚を通りがかる一人に渡してみた。
「ありがとう」
そう言って受け取ってくれた。なかなかいい反応だな、と思った。ぼくは少し調子に乗って、周囲の人垣に節操なく残りのフライヤーを渡し始めた。するとみんなありがとうと言って、素直に受け取ってくれる。日本で駅前のチラシ配りなどしてたら誰も見向きもしてくれないのだから、これはわりといい反応だ。そうして三十枚も配り終わった頃、人垣の中から一人の女性が声をかけてきた。
「ねえ、私にもそのチラシを分けてくれない?」
ぼくは安堵を通り越して少し嬉しくなった。彼女はフライヤーを見ながら言った。
「あなたもしかして、その自転車でアメリカを横断するつもりなの?」
ぼくは一通り自分のやろうとしていることを説明した。
「セーブ・ザ・チルドレンなら私も知っているわ。アメリカでも活動している団体よ」
彼女は興味を持ってくれたようだった。聞けば、彼女は十字架のデモンストレーションをやっているボランティアの一員なのだという。ぼくは彼女達がやっている活動の内容を聞いてみた。
「私たちはベテランズ・フォー・ピースという団体よ。メンバーの多くは元軍人なのだけれど、退役してから平和の為に活動している人達よ」
彼女の言った「退役軍人なのだけれど」の「けれど」が、いかにも軍人と平和は一般的には対極の概念なのだというニュアンスを帯びていて、それが少し引っかかった。
ビーチを埋め尽くす大量の十字架は、イラク戦争で既に亡くなっているアメリカ軍兵士のもので、亡くなった兵士の数だけビーチに立てられているのだという。ペンキで白く塗られた木製の十字架には、ひとつひとつ小さな花やミニチュアの星条旗などが供えられていた。
「私たちは、人が多い週末を狙って、毎週ここでデモをしているのよ。もう半年以上になるわ。本当はイラク人の犠牲者の十字架も一緒に立てるべきだと思うの。でもそうしたらサンタモニカのビーチをすべて埋め尽くさなければならないわ」
ビーチの一角の「墓地」を見つめながら彼女は静かに言う。この十字架は全部で何本になるのかとぼくは尋ねた。
「今のところ七〇〇本以上になっているわ」
そばで星条旗がぱたぱたと音を立てた。大量の十字架から重苦しさのようなものが伝わってくる。
これからも犠牲者が増えるごとに、この十字架も増えていくのだろうか。そして、犠牲者が増えることを見越して、もう何百本か誰のものかもわからない十字架をストックしているのだろうか。ぼくはそれが気になったが、なぜか聞くことができなかった。
十字架のそばには木製の展示台があって、イラク戦争に関する資料や、犠牲者たちの紹介があった。それを眺めながら、ぼくは日本のドキュメンタリー番組で見た米兵の犠牲者とその遺族の女性を思い出していた。
女性は、弟をイラク戦争で亡くしたといって嘆いていた。彼女はその怒りから戦争を擁護するのではなく、悲しみから戦争反対の意思を持っていると言っていた。そのことが印象的だった。
その犠牲兵の墓標が、今このビーチのどこかにある。ぼくの知るはずもないアメリカ兵の死のことが、日本で、アメリカで不思議な連鎖のように繋がった気がした。
そしてドキュメンタリーの女性だけでなく、ビーチを埋める七〇〇人分の遺族の痛みがあり、同じようにイラクやアフガニスタンやそれ以外の世界の地域紛争についても無数の人々の痛みがあることをぼんやりと思った。
ぼくはそれが「犠牲」と一括りにされて呼ばれることが、月並みだけれど、やはり不条理な気がした。そしてぼく自身も同じように一括りにし、そんな不条理に加担してきたのだと思った。
ぼくは人垣から少し離れた場所に立って、しばらく彼らの活動を眺めた。その光景はあらためて不思議なものだと思った。ポップコーン片手に砂浜を歩く人や、イヤフォンで音楽を聴きながらジョギングする人がそばを通り過ぎる。沖ではヨットの二枚の帆が午後の海風に少しだけ傾いていた。そしてその風景の一角に死者たちの十字架がある。
安穏と悲劇。互いに排斥しあうような二つのものごとが同じ風景の中に無言で同居している。それは一見不条理でありながら、一方で絶妙な均衡を保っているようでもあった。
ベテランズ・フォー・ピースの活動は、十字架を並べるだけのシンプルなものだった。拡声器で何かを叫んだり、声高に主張するということがない。ただ犠牲者の存在を提示しているだけだった。そこには怒りを訴えたいのか、悲しみを訴えたいのか、それさえもわからないような静けさがあった。
ぼくは彼女にこの活動を通して人々にどんなことを訴えたいのかと尋ねてみた。
「私たちはまず、犠牲者たちの存在を知ってもらいたいの。それは戦争の対価を私たちが知るということよ。イラク戦争には、賛成や反対やいろんな意見があるわ。でもどちらにしても誰もが答えを探しているの。それがあの戦争なのよ。だから私たちの活動が深く何かを考えるきっかけになればと思うの」
その言葉に、彼らの活動の立ち位置が見えた気がした。
週末の観光地には、イラク戦争に対する賛成や反対を含め、多様な意見があるに違いない。十字架の活動はそれらのすべてをやさしい眼差しで包みながら、一方である種の厳しさを突きつける。それはどんな結論であるにせよ、誰もが一度は戦争を深く考えてほしい、それだけは譲れないという厳しさだ。
ぼくはその厳しさを、彼らが活動の場を敢えて賑やかな観光地に選んだという決断の中に読み取った気がした。それはこの人波の中に入っていくことをつい数十分前まで躊躇していたぼくにはないものだった。
きっと彼らの活動が持つ静けさとは犠牲者への鎮魂であり、戦争に対する多様な立場への配慮でもあるのだ。ぼくはその姿勢を誠実なものだと思った。過去を生きた人間に対して、これからを生きる人間に対して、誠実なものだと思った。
「あなたの活動を取材してもらったらどうなの?今日私たちのデモの取材に来ている人がいるの。ジャーナリストよ。今呼んでくるから待っていなさい」
そう言って、彼女はぼくのフライヤーを何枚か持って、自分たちのテントの方へ戻っていった。ぼくは少し嬉しくなった。フライヤーを代わりに配ってくれるというだけでも有り難かったが、ジャーナリストを呼んで来てくれる。少なくともぼくがこの国でやろうとしていることに、何かを感じとってくれたのだ。そのことが嬉しかった。
しばらくして女性と共にやってきたのは、若い男のジャーナリストだった。細身でひげを蓄え、キャップを目深にかぶっていた。映画監督のスティーブン・スピルバーグに似ていた。そのことを彼に言うと、彼もまんざらでもない様子だった。
「ぼくはロサンゼルス・インディペンデント・メディア・センターというウェブサイトの記者だ。彼女から君のことを聞いてね。少し時間を貰えるかな」
そういうと、スピルバーグはおもむろにバッグからボイスレコーダーを取り出し、ぼくに突きつけた。
「ぼくが質問をレコーダーに吹き込んだら、君に向けるから、それで君が答える。その繰り返しだ。君の英語はパーフェクトじゃないけど、あとで編集するから気にしなくていい。さあ、始めよう」
そう言われて急に緊張を覚えた。この国に来て初めてインタビューを受けるのだ。今まで日本語でだってそんな機会はなかったのに、英語でできるのだろうか。好意でしてくれるはずの取材が障害のように思われた。
ぼくらは人垣から少し離れた場所まで移動すると、インタビューにとりかかった。一通りぼくの活動の内容や経緯や主旨についての質問が続いた。そしてそのあと、スピルバーグは戦争についての質問を始めた。
「日本でもアメリカのやる戦争に関して、多くの人が関心を持っているのか?」
新鮮な質問だ。当たり前のことだが、多くのアメリカ人は自分達の国の戦争を、世界の人々がどういう距離感で眺めているのか知るはずもないのだろう。
ぼくはイラク戦争が日本でもさかんに報道されていること、日本とアメリカの政治的な結びつきのことを簡単に説明した。
「アメリカの戦争は主にどういった影響を日本に与えるのだろう?」
ぼくはアメリカが戦争を始めると、同盟によって日本もそれをサポートすることになると答えた。
「日本ではそのサポートに対してどういう意見があるのかな?」
ぼくはそれから少し込み入った話をした。日本はもう六十年も戦争をしていないこと、イラク戦争では自衛隊を派遣することになったこと。湾岸戦争での「金だけ出して人を出さない」という国際社会の批判がその引き金になっていること。国内でも憲法九条を変えるべきだという動きが出てきていること。
ぼくはたどたどしい英語で答えたが、スピルバーグは気にしていないようだった。
「なるほど。確かにアメリカの動きは日本にも影響を与えているね。君はこの活動を通して戦争の是非を問う議論を喚起したいと言っていたけど、君自身は戦争そのものは必要なものだと思う?」
言葉に詰まってしまった。必要かというのは誰にとってのことだろう。そう思ったら素直に聞き返せば良かったが、なぜかできなかった。少し迷った挙げ句、ぼくは言葉を選んだ。
たぶん今、世界のどこかには自分の身を守ったり、大切な人を守ったりするのに武装しなければならない人々がたくさんいる。そんなやむを得ない人々を考えると戦争はあってはならないと簡単には言い切れない。けれども人間同士の殺し合いなどないに越したことはないし、国家や宗教や民族、政治的な対立を武力に転化しない努力はいつの時代も必要だと思う、と話した。
「ありがとう」
そういうとスピルバーグはレコーダーのスイッチをオフにした。緊張が解け、ホッとため息が出た。同時に自分自身が絞り出した言葉が、どこか空虚に宙を滑っていったのを感じた。けれどもその空虚さの本当の意味に気がつくのは、何年も後のことだった。
夕方になり、十字架の方も今日は引き上げる時間になった。ぼくは彼女のところに戻り、ジャーナリストを紹介してくれたお礼に後片付けを一緒に手伝いたいと申し出た。
ビーチに突き刺さった無数の十字架を一本一本はずして、十本ひとまとめにしていくのだ。
ぼくは砂の上に刺さった十字架を改めて近くで眺めた。よく見ると、十字架の一つ一つには個性があった。遺影のついたもの。メッセージの添えられたもの。花や小さな聖書が置かれているもの。カラフルに飾られたものや、シンプルなもの、色褪せてくすんでしまったものもあった。それらは遠くから眺めていたときよりも存在感があり、かつて生きていた人間をよりリアルに想像させた。
ぼくは彼女に言われた通りに、十字架を片付ける作業を始めた。顔写真をはずし、名前の書いたプレートをはずし、星条旗や花飾りをとりはずしていく。そして最後に名前のない真っ白な十字架だけが大量に残る。それらを十本一束にまとめて、ロープで縛っていく。
ふと、その作業過程は犠牲者の死がただの情報になってしまう過程に似ていると思った。こうしてかつて生きていた人間からその痕跡のようなものをはぎ取り、簡略化し、最後に無数の人間をいっしょくたにした、「犠牲者」という言葉だけが残る。
そうして記号化された言葉は、便利な反面、現実から重さのようなものを奪い取っていく。それがのっぺりした情報になって、ぼくらの手元に届く。そうした危うさのことをふと思わせた。
被害の当事者でないぼくは、彼らを一括りにし、のっぺりしたものとしてしか理解できないのだろうか。彼らの死を知るということと、その重さがわかるということは似ているようで、途方もない距離があるとぼくは思う。だとすれば、死者たちに誠実であるということはどういうことなのか。
ぼくは、出発前に周囲の人間に言われたことを思い返していた。
「犠牲者の痛みをわかりもしないのに、軽々しく反戦運動めいたことをするな」
そんな物言いの前に、ぼくはいつも立ち止まらざるを得なかった。そしてぼくはいつもそれを、心ならず犠牲になっていった人間に対して誠実であれ、というメッセージだと理解してきた。
ただ、その誠実であるということが、実際の自分にとっていったいどういう振る舞いのことを指すのか。それがずっと曖昧なまま、ぼくはアメリカまで来てしまった。そして今、十字架を束ねながらその答えの出ない問いのことを再び思い出していた。
やがてすべての十字架を撤去し、テントに戻って挨拶をすると彼女たちと別れた。
死者の十字架を掲げる人々と、それを取材するジャーナリスト。彼らはぼくが答えを出せないでいる問いに、自分なりの答えを出している人たちだ。あるいはそうすることで、はじめて戦争という不条理に対する立ち位置を見つけることができるのかも知れない。
ビーチを歩きながらそんなことを考えた。星条旗の向こう、銀色の海が静かに煌めいていた。

(つづく)
<目次>
【プロローグ】―なぜ戦争はなくならないのか―
【第一章・洗礼】―翌朝目が覚めると、さらに厳しい現実があった―
【第二章・ユダヤの眼差し】―「ユダヤもアラブもない。問題は人間のさがにある」―
【第三章・海辺の墓標】―怒りを訴えたいのか、悲しみを訴えたいのか―
【第四章・救命者の矛盾】―「自由を守るという物語に流されていったのよ」―
【第五章・渇きの果てに】―それらはあたかも暗い宇宙につつましく瞬く生命の輝きのようでさえあった―
【第六章・荒野の漂流者】―「日本でまた会おう」彼の言葉だけが耳の奥でリフレインしていた―
【第七章・逆境の中の生命線】―「闘いは嫌いだ。でも彼らをリスペクトしている」矛盾しているとぼくは思った―
【第八章・自由とは何か】―「自由万歳」を置き換えてみるとわりとよくわかる―
【第九章・オクラホマの風の中で】―彼女はこの場所でぼくと同じ歳で亡くなった―
【第十章・地図の上の1セントコイン】―それは戦争の是非を問うことと同じくらい大切なことに思えた―
【第十一章・ある記憶との闘い】―私は弱さを持った人間を探していた。どこかに自分と同じような人を探していたのよ―
【第十二章・シェルター】―ぼくは「彼ら」から逃げない人間になりたい―
【第十三章・マイノリティの居場所】―“There is no way to Peace,Peace is the way.A.J.Muste”―
【第十四章(最終章)・無限のざわめきの中へ】―その豊かさは残された救いのようでさえあった―
【著者プロフィール】
矢田 海里(やだ かいり) ライター・フォトグラファー。1980年、千葉県生まれ。慶応義塾大学総合政策学部卒。在学中、イラク戦争下のアメリカ合衆国を自転車横断しながら戦争の是非を問うプロジェクト“Across-America”を行い、この体験を文章にまとめたアクロス・アメリカを執筆。フィリピンのマニラのストリートに潜入し、子どもたちや娼婦たちの暮らしを見つめ、ルポルタージュを執筆中。東日本大震災発災直後に現地入り、ボランティアの傍ら現地の声を拾い始める。以降現地に居を構えながら取材を続ける。放送批評雑誌『GALAC』に「東北再生と放送メディア」を連載。冒険家やアスリートを紹介するサイト「ド級!」でエクストリーマーの一人に選ばれる。「不確かさと晴れやかさのあいだ」をテーマに人間の内面を描き続けている。
『かがり火』定期購読のお申し込み
まちやむらを元気にするノウハウ満載の『かがり火』が自宅に届く!「定期購読」をぜひご利用ください。『かがり火』は隔月刊の地域づくり情報誌です(書店では販売しておりません)。みなさまのご講読をお待ちしております。
年間予約購読料(年6回配本+支局長名鑑) 9,000円(送料、消費税込み)